東京日仏学院へ。「かつて、ノルマンディーで」を見る。1835年に起きたピエール・リヴィーエールによる父と妹殺人事件を分析したフーコーの研究書『ピエール・リヴィエールの犯罪』発行(1974)の2年後に、ルネ・アリオがこの事件を映画化する。映画は、ノルマンディーに暮らす全くのシロウトによって演じられたという意味で話題となった。その時に助監督をしていたニコラ・フィリベールが、30年後2006年に、同作品に出演した人びとを訪ね歩き、当時の思い出を語ってもらうというドキュメンタリー作品を発表する。それが「かつて、ノルマンディーで」だ。
この映画をテキストに廣瀬純さんが講演を行った。
「「わたしの人生はへたくそにモンタージュされ、へたくそに演じられ、うまくかみ合っていない吹き替え映画のようなもの」とマルグリット・デュラスは言ったが、リヴィエールもまたフーコーに同じことを語りえたのではないか。フーコーが、リヴィエールに見出した「物語=殺人の装置」もまた吹き替え映画をなしている。D=Gは言う。「マルクスが示すのはふたつの"主要な"要素が出会うということだ。一つは、脱領土化された労働者であり、彼は自由で何も持たない労働者となり、自分の労働力を売らなければならない。もう一つは、脱コード化されたカネであり、これは資本となり、労働者の労働力を買う能力を持っている」。ここで問題となっているのは、まさにへたくそにモンタージュされ、うまくかみ合っていないもう一つの吹き替え装置のことである。言い換えれば、二重化された装置のことではないか」。
二重化された装置は、解決不能な問題として問題の出題者へと送り返される。共訳不可能な問題としての問題。もはや、解決(ソリューション)は、最も陳腐で堕落した問題への単なる注釈に過ぎない。われわれは、問題の問題こそ、問いとして生き続けなくてはならないのだ。
物語と殺人、音と映像、労働と資本、「と」によって連結する二つのもの、こと、様態…。この共訳不能な、決定不能な問題こそが、システム=社会の問題の核心である。システム・ソリューションは、じつは問題そのものからの撤退でしかないということを、肝に銘じる必要がある。問題を解決したと思った瞬間、われわれは問題そのものから滑り落ちていくのである。というようなことを講演を聞きながら思ったのでした。
この映画をテキストに廣瀬純さんが講演を行った。
「「わたしの人生はへたくそにモンタージュされ、へたくそに演じられ、うまくかみ合っていない吹き替え映画のようなもの」とマルグリット・デュラスは言ったが、リヴィエールもまたフーコーに同じことを語りえたのではないか。フーコーが、リヴィエールに見出した「物語=殺人の装置」もまた吹き替え映画をなしている。D=Gは言う。「マルクスが示すのはふたつの"主要な"要素が出会うということだ。一つは、脱領土化された労働者であり、彼は自由で何も持たない労働者となり、自分の労働力を売らなければならない。もう一つは、脱コード化されたカネであり、これは資本となり、労働者の労働力を買う能力を持っている」。ここで問題となっているのは、まさにへたくそにモンタージュされ、うまくかみ合っていないもう一つの吹き替え装置のことである。言い換えれば、二重化された装置のことではないか」。
二重化された装置は、解決不能な問題として問題の出題者へと送り返される。共訳不可能な問題としての問題。もはや、解決(ソリューション)は、最も陳腐で堕落した問題への単なる注釈に過ぎない。われわれは、問題の問題こそ、問いとして生き続けなくてはならないのだ。
物語と殺人、音と映像、労働と資本、「と」によって連結する二つのもの、こと、様態…。この共訳不能な、決定不能な問題こそが、システム=社会の問題の核心である。システム・ソリューションは、じつは問題そのものからの撤退でしかないということを、肝に銘じる必要がある。問題を解決したと思った瞬間、われわれは問題そのものから滑り落ちていくのである。というようなことを講演を聞きながら思ったのでした。

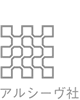








このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。